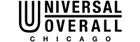WORKERS STYLE vol.12
WORKERS STYLE vol.12
ヘリテージパンツは完成していない。
ワークウェアとは、現場で履かれて働いて、初めてワークウェアとしての本来の意味・価値が伴う。着る人が自分の癖や働き方、思想を反映させるためのツールのような存在。ワーカーが自分の働くスタイルに合わせてカスタマイズし、それぞれのライフスタイルや価値観を表現していくアイテム。着る人の使い方やこだわりによって、ワークウェアは初めて「完成」されていく。このパンツがどんな風にその人にとっての欠かせない自己表現になるのか。ヘリテージパンツを通して、様々なワーカーにスポットをあてていく。

長池悠佳/活版印刷スタジオ デザイナー
1992年生まれ、東京都出身。大学ではグラフィックデザインを専攻し、現在はデザイン事務所併設の活版印刷スタジオにて、自社プロダクトのデザインと印刷、ワークショップを担当しながら、個人の作品制作にも取り組んでいる。
佳色
昔から、布や石、そういう“材”と呼ばれるものに惹かれる。どれも同じ表情がない。均質なものは、どこか物足りない。
紙もまた、僕を魅了する存在のひとつだ。液晶みたいに一様ではなく、一枚一枚に微妙なざらつきや光の吸い方があって、触れたときの感触も異なる。好きな雑誌を選ぶときも、紙質に左右されるくらいだ。
そして紙の持つ表情を決定づけるのが、印刷の技術だ。インクの乗せ方ひとつで、色は無限に変化する。中でも活版印刷は、ひときわ特殊な方法だ。刷り方がとにかく面倒くさい。一言で言うなら、手がかかる。けれど、その工程を経た紙には、たしかに自分の手を通ったという実感が宿る。
一辺倒ではない。だから惹かれるのかもしれない。
そんな手強い印刷技術を扱い続けている、日本でも数少ない活版印刷のデザイン事務所。そこで働く長池さんに話を聞いた。

―― お久しぶりです。朝早くに申し訳ないです。
長池:いえいえ、大丈夫です。こちらこそ、よろしくお願いします。印刷の工程も見ますか?
―― いいんですか? 体験してみたいです。
長池:ぜひぜひ。準備しながらでもいいですか?作業しながらのほうが話しやすいかもしれないので。

―― では早速、デザイン事務所で働くようになったのは大学生の頃からだったそうですね。
長池:はい。最初はエディトリアルデザインの事務所でアルバイトとして入りました。そんな中、社長が活版印刷の機械を導入し、手伝うようになったのが転機ですね。デジタルとは違い、インクの調整や紙の選定まですべて手作業で。最初は戸惑いましたが、試行錯誤しながら作業するうちに、手を動かす感覚がしっくりくるようになって。気づけば黙々と刷る時間が増えていました。スタジオが本格始動するタイミングで声をかけてもらい、そのまま続けることになりました。いつの間にか、この場所が自分の居場所になっていましたね。

―― 実際に手を動かすことの多い仕事なんですね。活版印刷というと、どこか昔の技術という印象もありますが、やはりアナログな部分が重要なんでしょうか?
長池:すごく重要ですね。例えば、デジタル上で「この色がいいな」と思っていても、実際に印刷してみると全然違って見えることがあるんです。紙の質感によっても、インクの乗り方が変わるので、頭で考えるだけじゃなく、実際に試してみないとわからない。そういう試行錯誤を繰り返すことで、ようやく「これだ」と思えるものにたどり着くんです。

―― そう考えると、色選びもデザインの重要な要素ですね。普段、色を選ぶ際に大事にしていることはありますか?
長池:ありますね。私は暖色系が好きで、特にピンクとオレンジの組み合わせが好きなんです。温かみがあって、ちょっと遊び心がある感じがいいなと。それに、黄土色と水色の組み合わせも好きなんですけど、たまに独特だと言われることがあります、、、。

―― 黄土色と水色、確かに少し独特な組み合わせですね、僕は好きですが。その配色はどんなふうに活かされているんでしょう?
長池:実際にデザインしたノートが、表紙を黄土色にして、帯を水色にしたものがあって。その組み合わせにするだけで、ノートが持つ雰囲気がガラッと変わるんです。私の中では、どこか懐かしさを感じる色の組み合わせなんです。でも、他の色の方が人気はありそうです(笑)。それでも、個人的にはすごく大事な色です。

―― 色の組み合わせで、印象はかなり変わりますよね。その感性の参考にしているのはものとか人とか何かあるんですか?
長池:ロスコっていう画家の作品をよく見ますね。彼の色の使い方って、単体の色というより、隣にある色との関係性で印象が決まるような気がしていて。同じ赤でも、隣に青があるのと黄色があるのとでは、全然違う見え方になりますよね。デザインの仕事でも、そういう視点を大切にしています。

―― 仕事の中で、色を選ぶ機会は多いですか?
長池:多いですね。それこそノートを作る時なんかは、「今回は12色でいきましょう」と決まると、それぞれの色の組み合わせを考えるんです。全体を並べた時にどう見えるか、単体で見た時にどう感じるか。そういう試行錯誤をするのは大変ですが、楽しい時間でもありますね。

―― 色と形が組み合わさって、初めてデザインとして成立するんですね。そういう意味で、ワークウェアにもデザイン的な要素はあると思いますが、ヘリテージパンツを履いてみてどうでしたか?
長池:すごく動きやすかったです。印刷や製本の仕事って、しゃがんだり立ち上がったりの動きが多いので、ストレスなく動けるのがいいですね。それに、汚れても気にならない色味というのは、仕事着としてとても大事なポイントです。

―― ワイドシルエットいいですよね。僕も近い感覚でストレスなくっていうのは大事な気がします。逆に、ここはこうしてほしいな、みたいなのはありますか?
長池:うーん、しいて言えばウエストが大きいサイズしかまだないですよね、そのくらいですが、ベルトで絞めればあまり気にならないので、そう考えるとあんまりないかも?愛用させていただいてます。

デザインとは、選び続けること。色を選び、形を選び、素材を選ぶ。
その小さな積み重ねが、日々の輪郭を作っていく。
長池さんが服を選ぶ時も、似た感覚なんだろうなとふと思う。
その中でヘリテージパンツは選択肢に入っていて、いつの間にか仕事を支えている。
些細なことだけど、自身が関わるものが誰かのクリエイションの一部になっているのは、やっぱり嬉しい。
作業を始める時、意識せずに手に取る。それはつまり、そういうことだ。
どこか余白がある。
余計なものを削ぎ落とした美しさ、ではなく、まだ“選べる”余白。色を置く場所、紙の質感、印刷の濃淡。その余白があるからこそ、デザインは広がり、手の中で少しずつ形になっていく。デザイン事務所の奥、静かに重なる紙の束。
活版印刷の跡。少し擦れたインクの風合い。
選ばれたものたちが並ぶその風景に、彼女の毎日は確かに息づいている。
黄土色と水色の合わせが僕の佳色になった日。


text and photograph by hilomi